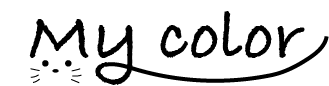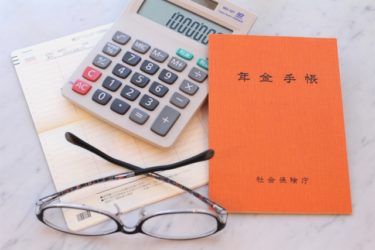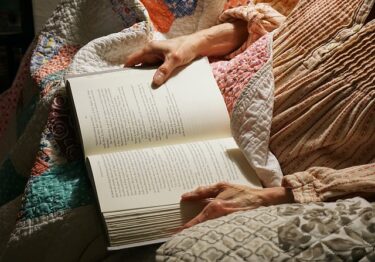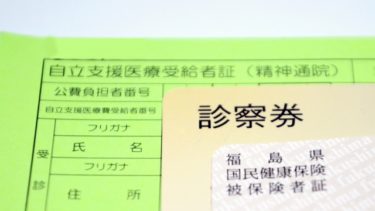多重介護、老老介護という言葉はすでに世の中に浸透しています。
介護をひとりで抱え、周囲にどんな救いの手があるのか分からない人もいるのではないでしょうか。あなたの近辺、地域、社会に頼れるものはありますか?
介護をひとりで抱えていませんか?
要介護者のいる家庭では、介護のほとんど、または全てを特定の一人だけで担う状況が少なからず見られます。
要介護者と二人暮らしといった家族構成ならば、介護する人は要介護者でない方となる場合が大半でしょう。
しかし複数の家族がいても介護を担当するのは決まった一人、複数の要介護者を一人で介護しているという状況も珍しくありません。
身近な存在である家族がサポートすることは望ましいことですが、家族だから必ずしも介護しなければならないという義務はありません。
だから介護に協力しない家族がいてもやむを得ないし否定はしない。しかし私が第三者の立場で在宅介護をしている家庭に立ち入り、誰か一人だけが介護を引き受け、一人だけが犠牲になっている状況をみると、もっと他に方法がないものかと引っかかりを感じるのです。
介護の偏りの背景
介護分担に偏りが出るのは仕方がないことです。
介護をどこまで背負えるかは、仕事や生活の事情、要介護者との関係性なども影響してくるため、やむを得ず協力できない人もいます。
しかし家庭の中で介護をする人・しない人に極端に分かれてしまうのはなぜでしょう。
要介護者の性別
介護者の7割超が女性です。
特に介護者の立場になりやすい60代以降の世代では、1980年代に定着した一般的な家庭内分業の在り方を引きずり時代を越してきたことが考えられます。
「男性は仕事、女性は家庭」といった性別役割分業の固定的な意識がいまだ根強いのは否定できません。
女性側の意識として、「自分がやらないといけない」「自分がやった方が早い」などと自らに義務を課してしまう考え方も見られます。
同別居の状況
介護者の7割以上は、要介護者と同居する立場にいます。
物理的、時間的理由からも同居者が介護した方が効率的です。介護を必要としている人にとって自分が一番身近な存在ならば、何とかできるのは自分しかいないという考えは当然です。
しかし同居しているからといってすべてを引き受けなければならない、自分を犠牲にするしかならないというのは早まった考え方ではないでしょうか。
様々な事情
介護に携われない人にも様々な事情があることは想像できます。要介護者への思いや辛い記憶、自分自身の問題(体調や多忙など)、物理的・金銭的な問題もあるでしょう。
いろんな事情を理解できるため、介護に携われない、協力したくないという人に対して、すべてが薄情だとは思いません。介護と距離を置くことも選択肢の一つです。
一人で抱え込むといろんなことが上手くいかなくなる
「できるのは自分しかいない」と一人で頑張りすぎると、自分だけでなく要介護者の負担も増すことになりかねません。
介護者の疲れが蓄積し精神的に追い込まれると、つい態度がきつくなったり、要介護者を待つ余裕がなくなり、自立や自尊心を妨げることにもつながります。
「このままじゃいけない」「何とかしなきゃ」との焦りや、「なぜ自分ばかり」と被害意識が生じ家族間の亀裂が生じることもあります。
介護をきっかけに介護うつや燃え尽き症候群を発症する人もいます。
うつ病は真面目で完璧にやろうと頑張りすぎる人に起こりやすい病気です。
ひとりで頑張った結果、体調を壊し介護に責任を持てる人がいなくなっては何もなりません。
あなたが負えるのはどこまでですか?

目の前に助けを必要としている人がいて、力になりたい、自分がやらなければと思えるあなたは、思いやりがある温かい人です。
しかし介護を必要としている親や配偶者などを心配するあまり、自分自身の状況を冷静に見ることができなくなってしまうことがありませんか?
あえて一度介護から離れて、自分の状況を振り返るのをおすすめします。
- 現在の自分の生活において、どれくらいの身体的・精神的な負担を負えるのか
- 体調面での不安はないか
- 犠牲にできないものは何か(子供との時間、仕事、たまにひとりになれる時間など)
- どれくらいの資金を介護に費やすことができるか
(当面の収入と支出、家族や職場のイベント、ローン、子供の教育費など予測できる出費などをふまえて)
このようなことを書き出してみると自身の状況を客観視できます。
状況が不透明なまま介護を続けていくと、介護上の課題も自分自身の課題も中途半端にしか解決できず、不安や焦りが蓄積するばかりになってしまいます。
他の家族は協力してくれそうですか?
介護全般に協力できないとしても、以下のようなことで力を借りることができませんか?
- 体調が悪い時や外せない用事がある時に介護を変わってもらえるか
- 相談にのってくれるか、アドバイスをくれるか
- 資金的な援助をどこまで負えるか
- 直接介護以外のこと(通院時の送迎、介護用品の補充など)だったら頼めるか
- 長期的ではなく、余裕のある時にだけ声を掛けてもらえないか
- 協力しなくても気にかけてくれるか
ほかの家族の得意・不得意を見分け、適材適所を作り出すことができるかもしれません。一方でできない家族に期待しすぎると、精神的疲労は大きくなります。場合によっては見切りがないと割り切ることも必要です。
要介護者の自立心に頼る
要介護者にできることがあればやってもらった方が、自発性を高め残存機能維持につながります。ベッドサイドに飲み物や歯磨きなど、自分で使えるものを置いておけば仕事は減ります。
介護者が先回りしてやっている介護は結構多いものです。全てやってもらうよりも、自分のペースで好きなようにやれる環境があれば、本当は後者の方が助かるのではないでしょうか。
1から10までやってあげるのではなく、セルフケア能力や普段の日常生活に合わせて必要な物・環境を予め用意することで、減らせる介護負担はありませんか。
頼れる場所を見つける
社会資源、民間資源で活用できるものはあるはずです。介護をしながら仕事を続けたい、夜間の休息が欲しいなど、介護者の生活状況も踏まえて改めて介護体制を再検討することも時には必要です。
以下のサービスはほんの一部ですが、ケアマネージャーや市町村窓口に相談してみることをおすすめします。
(介護保険サービス)
・ショートステイ、医療型短期宿泊施設
・訪問介護、訪問入浴
・デイケア、デイサービス
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回随時対応型訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅介護
(民間や地域の資源)
・配食サービス、買い物代行、スーパーの宅配
・家事代行
・ボランティア
・見守りカメラ、見守りセンサー
相談場所
・地域包括センター:介護に関する総合的な相談に対応
・保健所:保健師が中心となり健康相談に対応
・介護者ホットライン:介護者自身のメンタルヘルスケア
・ボランティアセンター:社会福祉協議会のなかにあり、ボランティアについての情報を提供している
・自治体の高齢者福祉窓口:介護費用や社会保障の情報提供
介護者の価値観
「介護は誰がするもの」と偏った価値観があれば、多様化する介護方法についていけず、ひとりで介護を抱える状況を変えていくことができません。
介護者の価値観は、要介護者や周囲の家族にまで影響します。
介護をひとりで頑張り過ぎてしまったことが裏目に出て、要介護者が「迷惑を掛けたくない」「長生きしなくない」と悲観的になったり、周囲の家族が後ろめたさを感じ介護に口を出せなくなるという状況が実際にあります。
自らの仕事や趣味、睡眠を犠牲にし、介護をひとりで抱えているのなら、一度立ち止まってみてください。介護と距離を置くことを安易に勧めるつもりはありません。しかし他の方法を一つでも見つけることができると、介護に対する価値観を少しずつ塗り替え、協力者の存在、要介護者の思いなど新たな発見があるはずです。