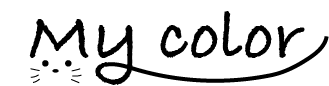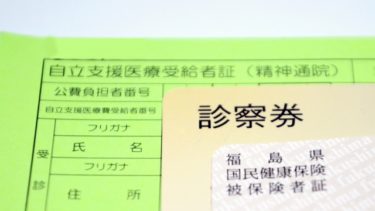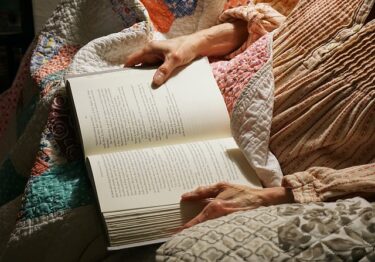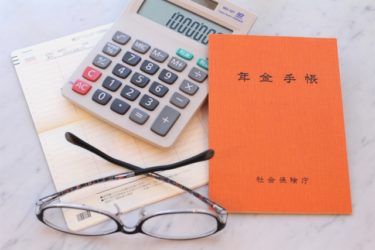自宅で点滴をする場合、管理上の理由から中心静脈カテーテル(CV)を選択されることがよくあります。末梢血管(手や足などの静脈)と異なり、閉塞のリスクが低く、細い血管に何度も針を刺し苦痛を与えることはありません。注意点はいくつかありますが、それを押さえれば医療者でなくても安全に管理することができます。
中心静脈カテーテル(CV)・中心静脈栄養(IVH)とは

まず、中心静脈カテーテル(CV)について簡単に説明します。
中心静脈とは心臓に近い部分に位置する静脈です。末梢の血管とは違い太く、滞りなく血液が流れています。そこに長さ数十センチのカテーテルを挿入し、円滑に輸液を流すことができるのが中心静脈カテーテルです。
留置する部位は概ね以下から選択されます。
・鎖骨の下にある鎖骨下静脈
・首の横面あたりの内頚静脈
・鼠径部あたりの大腿静脈
中心静脈栄養(IVH)は、①食事が摂れないとき ②水分・電解質の調整が必要なとき ③栄養状態の改善が必要な場合に、中心静脈カテーテル(CV)から高カロリー輸液などを行うことをいいます。
中心静脈カテーテルのメリット
✔️ 長期間留置が可能
感染や閉塞等のトラブルが生じなければ、差し換えせずに留置していることが一般的です。
✔️ 閉塞の可能性が低い
末梢の血管であれば、留置している腕を上げたり曲げると血液が逆流したり停滞することがありルート閉塞を起こしやすくなります。CVの場合は太いルートを太い血管に入れているため、閉塞のリスクが軽減します。
✔️ 動作が少ない体幹部へ留置するため、活動への支障が少ない
手足の動きを制限されることがないため日常生活動作で感じる不便を軽減できます。
その一方で、内頚静脈であれば首の動きが制限され、大腿静脈であれば歩いたりする場合に支障を感じます。生活動作も一つの判断材料にし留置部位を決定しています。
✔️ 末梢血管では投与できない薬剤・製剤を投与する場合に選択される
浸透圧が高い薬剤を末梢血管から投与すると、静脈炎を起こし痛みや腫れ、時に発熱や悪寒などの全身症状を引き起こします。CVでは末梢点滴に適応しない高濃度の栄養剤、電解質、アミノ酸液などを投与できます。
自宅での中心静脈栄養・輸液療法

カフティ―ポンプで滴下調整や異常感知をおこなう
自宅で中心静脈輸液をする場合、カフティーポンプという自動の滴下調整装置を使用します。カフティ―ポンプで予め設定した滴下速度を維持し、滴下調整を手動で行う必要はありません。
閉塞や気泡、空液の場合はアラームと画面表示で知らせ、下記の確認をする必要があります。対処後に「開始」ボタンを押すと再び滴下がはじまります。
✔️ 「閉塞」 ルートが圧迫されていないか、折れ曲がっていないか
✔️ 「気泡」 ルート内に空気が入っていないか
✔️ 「空液」 点滴バックの中身が空になっていないか
アラームで感知されないのはルートからの液漏れです。点滴の接続部はねじ込み式で外れにくくなっていますが、接続する際は緩くないかを確認しましょう。またルートの途中に三方活栓(別のルートを繋げる接続部品)がついている場合は固定が緩くなっていることがあるので注意しましょう。
中心静脈カテーテル管理のポイント
① 汚さない
保護しているドレッシング剤に隙間ができている場合はテープを重ね補強しましょう。入浴する場合は、CVは防水のフィルムで保護されているのでそのまま入っても良いですが、隙間があればドレッシング剤で補強してください。鼠径部に留置している場合は排泄物が付着し汚染されやすいため、おむつはこまめに交換し清潔を保つようにしましょう。どうしてもドレッシング剤が剥がれやすい、汚染しやすい状況であれば、看護師へ報告し保護の仕方に工夫が必要です。
② 抜けさせない
意識が不清明または認知症の場合は、無意識にいじってしまい抜去の可能性があります。ルートを目の届かない位置に配置、ルートの固定を強化、ルートを寝衣の中に入れ隠すなど、触れないようにする工夫が必要です。
どうしても対処が困難な場合は医師や看護師へ相談しましょう。状態にもよりますが、投与時間の調整などを検討することもあります。
③ 閉塞させない
カフティ―ポンプのアラームは「閉塞しそう」という知らせです。アラームが鳴ったらすぐに対処すれば閉塞することは殆どありません。
同居されている方が複数いる場合は、皆がアラーム対処方法だけでも知っていた方が安心です。また利用者のそばを長時間離れる前は、「ルートの位置が適切か」「薬液の残量は問題ないか」「ポンプのバッテリーは足りるか」を確認しておきましょう。
中心静脈カテーテルのトラブル対処法
<カテーテルを抜いてしまった>
カテーテルは通常皮膚に3か所縫い付けることにより固定されています。普段の生活で抜けることはありませんが、強く引っ張ると抜けてしまうこともあります。
抜けてしまったら、まずすぐにやるべきことは止血です。挿入部をしばらく圧迫止血すれば出血は止まります。慌てずガーゼや清潔な当布で止血をし、その後に医師や看護師を呼びましょう。
<ルート閉塞してしまった>
ルート内で血液が凝固して起こります。長時間経っていなければ開通できる可能性が高いです。シリンジタイプの生理食塩水またはヘパリン加生食水があれば、ルート接続部より注入してみます。それでも滴下不良が続けば医師への報告が必要です。
<気泡が入っている>
小さな気泡が僅かに入っているだけなら特に問題はありません。大量の気泡が入っている場合はいったん滴下を止め、カテーテルからルートを取り外してルート内を薬液でを満たします。ルートの上部にある気泡やフィルターに溜まった気泡は、指でトントンと叩くようにすると上にあがって抜けます。
緊急連絡のポイント
下記のような状態があればすぐに訪問看護師や担当医へ連絡しましょう。
✔️ カテーテルのトラブル:ルート抜去、損傷、裂傷、液漏れ
✔️ 挿入部のトラブル:発赤、腫脹、皮膚の異常
✔️ 全身症状:発熱、悪寒、尿量異常、傾眠、嘔吐など
(血糖異常や電解質異常などの急激な症状)
✔️ カフィ―ポンプのアラームが解消できないとき
定期的に行う管理
① ルート交換
点滴ルート(中心静脈点滴セット)の交換は週に1回の頻度で行います。(点滴セットの発注数などで多少のズレは問題ありません)
24時間持続輸液しない場合は、取り外した点滴ルートは袋などに入れ清潔に扱いましょう。また使用前はアルコール綿で接続部を拭きましょう。
② 刺入部の消毒
通常週に1回以上行います。刺入部の観察なども含めて看護師が行うことが多いですが、汚染時などは介護者が行わなければなりません。医療者からやり方の指導を受けましょう。清潔な手で行う、刺入部に触れない、消毒後は空気が入らないようフィルムで密閉することがポイントです。
中心静脈栄養法・輸液による合併症

カテーテル感染
カテーテル挿入部の汚染、ルート接続や消毒時の不適切な取扱いなどが原因で、カテーテルより微生物が侵入し感染症を引き起こします。発熱、悪寒・戦慄のほか、挿入部の異常(発赤・熱感・腫脹)などを生じます。特に免疫が衰えている療養者の方は、感染が全身に蔓延し重症化するケースがあります。
空気塞栓
血管中に大量の空気が入り込むことで、全身に障害を来します。脳血流に支障を来すと意識障害、感覚障害、麻痺を生じ、肺塞栓では呼吸困難などを引き起こします。
僅かな空気であれば肺で代謝され身体に害を与えることはないため、神経質になることはありません。
対策としてはルート類を開放したままにしていないか、ルート類の外れがないか、薬液バックが空のまま滴下していないかを確認することです。カフティ―ポンプには気泡を知らせてくれる装置が備わっており「空液」には気付くことができますので、アラーム時に速やかに対応すれば問題はありません。しかしポンプ機器を通さない部分のルートに三方活栓などの接続品があればそこからの空気の流入は感知できません。自宅では正常なルートの状態(接続が締まり、ルート内に空気がない)を確認するようにすれば防止につながります。
血栓症
血管の中に血栓(血の塊)を作り、血流を遮断することで全身の症状に発展します。カテーテル留置部の腫脹、発赤・硬結が生じ、血栓が他臓器に流れると、脳梗塞や肺塞栓、心筋梗塞などを引き起こします。
血栓症の原因は利用者の体調面が影響し、動脈硬化や糖尿病など血液が固まりやすい病気、心疾患で全身循環に異常がある人が発症するリスクがあります。
自宅でできることは、カテーテル閉塞して滴下不良の状態を放置しないこと、カテーテル挿入部に異常がないかを観察することです。